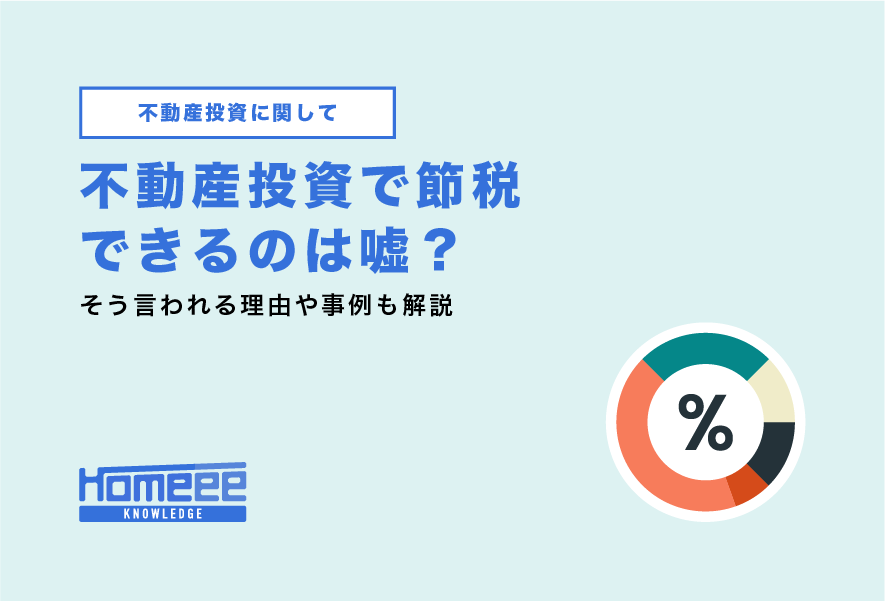不動産投資は「節税になる」とよく言われますが、実際には誤解されていることも多く、期待したほどの節税効果が得られないケースも少なくありません。
確かに一部の税金を軽減できる可能性はありますが、節税だけを目的に始めると失敗するリスクが高まります。
この記事では、「不動産投資で節税できる」という説が本当なのか、それとも誤解なのかを具体的に検証していきます。
不動産投資で節税できるは嘘?

結論として、「不動産投資で節税できる」という考え方は一部正しいです。しかし、それほど大きな節税は期待できないという点では一部誤解を含んでいます。
確かに経費や減価償却を活用することで、一時的に所得税や住民税の負担を軽減することは可能です。ただし、赤字を前提にした節税は長期的に見ると不利に働くことがあり、節税だけを目的にすると投資本来の利益を得られなくなる恐れがあります。
不動産投資によって節税できる可能性がある税金は以下の通りです。
・所得税:不動産所得が給与所得と損益通算できる場合
・住民税:課税所得に応じて変動
・相続税:評価額を下げられるケースがある
不動産投資で節税は嘘と言われる理由

①経費が発生することで節税を実感しづらい
不動産投資で節税が可能とされる主な理由は、管理費や修繕費、ローン利息などを経費として計上できる点にあります。
これにより課税所得を減らすことはできますが、経費が多いということは実際に現金が支出されているということでもあり、「節税できたはずなのに手元にお金が残らない」と感じるケースも少なくありません。
そのため、節税効果を実感しにくく、資金繰りに注意が必要です。
②投資用マンションは住宅ローン控除の対象外と知らなかった
住宅ローン控除はマイホーム購入時に適用される制度であり、投資用不動産には対象外です。
そのため、「ローンを組めば控除が使える」と誤解して投資を始めた人が、後になって適用外と知り落胆するケースが少なくありません。
控除を前提に返済計画を立てていた場合、想定が崩れて資金繰りが厳しくなるリスクも高まります。
制度の適用条件を正しく理解したうえで、慎重に資金計画を立てることが重要です。
③土地は減価償却できない
建物部分は耐用年数に応じて減価償却できますが、土地は対象外です。そのため「高額な土地付き物件を買えば節税できる」と誤解すると、思ったほど経費計上できず、節税効果は限定的です。
特に都心部のアパートやマンションは土地の割合が大きく、建物部分の減価償却だけでは期待したほどの節税につながらないケースが多く見られます。
たとえば、土地建物総額が1億円でも、土地が9,000万円、建物が1,000万円という内訳では、減価償却できる金額が限られます。
節税を重視するなら、土地と建物の価格配分のバランスにも注意を払う必要があります。
④空室や家賃滞納などのリスクを考慮していなかった
不動産投資は安定収入を期待されがちですが、実際には空室や家賃滞納といった不確定要素が常に付きまといます。
収入が減っても、ローン返済や固定資産税、管理費などの支出は止まりません。
こうした状況が続けば、節税どころか赤字が拡大し、生活資金にまで影響を及ぼす可能性があります。
収益性だけでなく、リスクへの備えも含めた慎重な資金計画が不可欠です。
不動産投資を成功させるには?

物件選びを徹底的に行う
物件選びは不動産投資の成否を左右する最重要ポイントです。
表面利回りや立地だけで判断するのではなく、将来的な人口動態や再開発の動き、周辺の競合物件の状況まで把握することで、収益の持続性を見極めることができます。
加えて、築年数や修繕履歴を確認し、今後必要となる修繕費用を見積もることも欠かせません。
購入価格に対して適正な家賃収入が得られるかどうか、シミュレーションを通じて長期的な収支バランスを検証することが重要です。
長期目線での資金計画を立てる
不動産投資で重要なのは、初期の節税効果よりも、長期にわたって安定した収支を維持できるかどうかです。
ローンの返済は20〜30年続くため、家賃の下落や金利の上昇、修繕費の増加などのリスクをあらかじめ見込んだうえで、計画を立てる必要があります。
さらに、設備の故障や建物の老朽化によって、思いがけない修繕費が発生することもあります。こうした事態に備えて、常に余裕資金を確保しておくことが、安定した運用と破綻の回避につながります。
節税できるのは購入後の数年間に限られるため、その後は利益を減らさず、大きな支出を避けることが投資成功のポイントになります。
専門家に相談する
不動産投資には融資、税務、法律など多岐にわたる知識が求められるため、専門家の力を借りることが重要です。
税理士に相談すれば、損益通算や節税の具体的な方法を把握でき、不動産コンサルタントからは立地や将来性に関する判断材料を得られます。
さらに、金融機関の担当者や弁護士と連携しておけば、万が一トラブルが起きた際にも冷静に対応できます。
独学では見落としやすいリスクを避け、投資の成功率を高めるためにも、専門家の視点を積極的に取り入れる姿勢が欠かせません。
節税目的で不動産投資をするべき人とそうでない人

不動産投資で節税を狙う場合、特に効果が大きいのは課税所得が900万円を超える高所得層です。
たとえば所得税率が33%以上の人であれば、経費を計上して課税所得を圧縮することで、節税額もそれだけ大きくなります。
一方で、課税所得が900万円未満の人は税率が低いため、同じ経費を使っても削減できる税額は限られ、かけた手間やリスクに見合わないこともあります。
そのため、節税だけを目的にするのではなく、将来的な資産形成や老後の備えといった長期的な視点で投資判断をする方が現実的です。
節税目的で不動産投資をして失敗した事例

節税効果を過信して赤字経営に
「経費を増やせば節税できる」と考え、修繕費や広告宣伝費を積極的に使った結果、帳簿上は確かに節税できたものの、実際には手元資金が大きく減ってしまいました。
家賃収入を上回る支出が続き、キャッシュフローは常に赤字で、本来は余裕を持って返済すべきローンも重荷となり、資金繰りは破綻寸前まで追い込まれました。
経費を使えば税負担は減りますが、使った分以上に節税できるわけではありません。
節税ばかりを意識しすぎたことで、投資の本来の目的を見失ってしまった典型的な失敗例といえます。
空室リスクを見誤ったケース
「駅近なら空室リスクは低い」と安易に判断して投資したものの、実際には周辺に新築物件が次々と建ち、競争が激しくなってしまいました。
その結果、空室期間が予想以上に長引き、家賃収入は計画を大きく下回る事態に陥りました。
さらに入居者の滞納も重なり、安定収入どころかローン返済や管理費の支払いで資金繰りが厳しくなったのです。
節税どころか生活費を補填する事態にまで発展し、立地だけで安心と考え、長期的な収支シミュレーションを怠ったことが大きな失敗につながったケースです。
まとめ
「不動産投資で節税できる」という言葉には一定の根拠がありますが、それを鵜呑みにすると思わぬ失敗につながる可能性があります。
所得税や相続税の面で効果が出るケースは確かにありますが、実際には経費の負担や空室リスクなども伴うため、期待したほどの節税効果を実感できない人も少なくありません。
節税はあくまで投資に付随するメリットの一つであり、目的そのものではありません。
不動産投資の本来の目的は、安定した資産形成を長期的に実現することです。
短期的な節税にとらわれず、将来を見据えた計画的な運用こそが、不動産投資を成功に導く鍵となります。